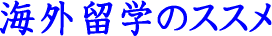
高校生海外留学の手順(2017年2月改訂)
1.準備スケジュール
短期留学を旅行会社や留学エージェントに申し込む場合は、留学の1か月前でも間に合うようです。しかし交換留学の場合は、留学の1年以上前から準備しないと間に合いません。多くの国際教育交流団体では、高2の夏からの1年間の交換留学(交換留学生の多くが選ぶアメリカに留学する際の一般的なパターン)の場合、高1の4月(留学する1年4か月前)から申込受付を開始しています。高1の夏からの交換留学の場合は、中3の4月からの申込受付です。
交換留学の選考試験は5〜6月ころから始まり、冬ころまで複数回実施されます。ほとんどの団体では、何度でも再受験できるので、1回目の試験から受験するのがベストです。落ちても次の試験までに一所懸命英語を勉強すれば、次は合格できるかもしれません。また奨学金を申し込むためには、申込期限があるため比較的早い時期の選考試験に合格する必要があります。
2.資料入手
インターネットで検索して、旅行会社や留学エージェント、民間国際教育交流団体などから資料を送付してもらいましょう。
民間国際教育交流団体としては、AFSがもっとも歴史が古く、ホームページ上で留学に関する各種の調査資料を配付しています。年間の留学生の派遣人数で比較すると、規模が大きいのはAFS、WYS、YFUの3団体です。
AFS日本協会
WYS教育交流日本協会
WFU日本国際交流財団
旅行会社や留学エージェント、民間国際教育交流団体などでは、年間を通じて説明会を開催しています。内容は、海外留学の現状、企業/団体の活動概要、体験者の話、派遣先国の現状紹介などです。質問や相談もできます。気に入った企業/団体があったら、説明会に必ず参加し、詳しい話を聞いておきましょう。
3.親と相談
親から「留学に行って来い」という話が出ればラッキーですが、そんなことは滅多にありません。「留学に行きたい」と決意した子供が、渋る親を何とか説得して、留学を実現するというパターンが普通です。AFSが参加した留学生を対象に2002年に実施した調査によると、家族や学校の先生から留学することに反対された人の割合は21%、そしてそのうち34%が保護者で28%はその他の家族・親族でした。
親が心配したり反対したりする理由は、主として以下の3点です。
(1)1年遅れで高校を卒業することになる(交換留学)
(2)大学受験で不利になる(交換留学)
(3)選考試験に受かるはずがない(交換留学)
(4)果たして留学先でしっかりやっていけるのか疑問
(5)経済的負担が大きい
(1)については、自分の学校の制度を調べて、留学扱いできる学校であるならば、同級生と同時に卒業することができることを説明しましょう。休学扱いしかできない学校であるならば、1年間の遅れは出るがそれ以上に大きなものを得られる、一生の間役に立つ貴重な経験ができる機会であることをアピールしましょう。
(2)については、休学扱いにすれば大学受験のために残された時間は同じなので、不利にはならないこと、そして英語圏へ留学すれば英語力は向上するのでこの点では大学受験で有利になることをアピールしましょう。
(3)は対応が簡単です。しっかり勉強して、選考試験に受かればいいのです。
(4)は、日ごろからの生活態度が重要です。「日本の高校生はいろいろな面で自立しておらず、中学生の延長のような、つまり大きな子供として生活している者が多いが、海外、特に欧米においては、高校生になったら自立して小さな大人として生活していくことが求められる」と言われています。「比較的何でも自分でできる方だ」と思っていても、留学先で自分の未熟さや生活ノウハウの足りなさを痛感する日本人留学生は、けっして少なくありません。
したがって、起こしてもらわないと学校に遅刻する、炊事洗濯掃除は親まかせなど、これまで親に対する依存度の高い生活をしてきた場合は、留学先でしっかりやっていけない可能性が高いです。これを機に悔い改めて、自分の生活能力を向上させて、しっかりやっていけることをアピールしましょう。炊事洗濯掃除は、受験勉強よりも簡単です。
(5)は、なかなか難しい問題です。「そんな金はうちにはない」と言われてしまうと、打開策がありません。高校生になってからバイトを始めても、50万とか100万の金は短期間では貯まりませんし、短期間で貯めようとすると勉強する時間がなくなり学校に行っても寝ているだけになって落ちこぼれます。しかし、それでも可能性はゼロではありません。奨学金があります。たとえばAFSの2017年出発の交換留学の場合は17種類の奨学金(うち5種類は全額支給)があります。
4.学校の先生と相談
交換留学に応募する場合は、学校長または担任教師の推薦書や、学校が発行する成績証明書などが必要です。また、交換留学から戻ってきたら留学扱いになるのか休学扱いになるのかは、大きな問題です。そのため、交換留学を志望する場合は、入手した資料を持参して、学校の先生に相談しましょう。短期留学の場合も、担任した生徒を留学に送り出したことがあるなど、留学について詳しく知っている先生がいるかもしれません。
なお、AFSが参加した留学生を対象に2002年に実施した調査によると、家族や学校の先生から留学することに反対された人の割合は21%、そしてそのうち25%は学校の先生の反対でした。通常の学校生活を維持することを重視し、それを逸脱する行為に対して批判的な雰囲気のある学校では、学校の先生が反対する場合があるようです。
5.留学扱い/休学扱いの選択(交換留学)
交換留学で1年間海外で過ごして、元の学校に復学する際には、同学年に復学する(高2で出発したら高2に復学)する休学扱いと、次の学年に復学する(高2で出発したら高3に復学)する留学扱いがあります。どちらになるのか、またはどちらかを選べるのかは、高校により異なります。AFSが参加した留学生を対象に2002年に実施した調査によると、参加者が通っている高校の規定は、休学扱い:23%、留学扱い:14%、選べる:54%、となっています。
実際に休学扱いと留学扱いのどちらかになったのかは、団体により異なります。AFSの留学のしおり(選考試験合格者に配布される資料)2006年版によると、交換留学に参加した生徒の希望としては、50%前後が留学扱いを希望し、その85%前後がそれを認められています。この結果、留学扱いになった者は42.5%前後、休学扱いになった者が57.5%でした。
6.申込
交換留学の場合はいろいろな書類があり、推薦状や成績証明書などは担任の先生や校長先生に書いていただかなければなりません。時間的な余裕をたっぷりと取って、早めに書類作成を開始しましょう。短期留学の場合は、パスポートや顔写真などを用意すれば、比較的申込は簡単です。
7.選考(交換留学)
選考試験の受験料は20000円程度です。選考試験の内容は、英語のテスト、一般常識のテスト、グループディスカッション、面接などですが、団体により、また選考方法により異なります。
英語のテストでは、おおむね英検3級(中学校修了程度)〜準2級(高校在学程度)の英語力が求められますので、中学校でしっかり英語を勉強しておく必要があります。一般常識のテストは、問題の難易度はそれほど高くありませんが、幅広く世の中の動向を知っておく必要があります。面接は極めて重要で、本人が留学について真剣に考えていないと判断されると、いくらペーパーテストで高得点でも不合格となります。
8.外国語の勉強
出発するまでの間に、現地の言語(特に会話)を一所懸命に勉強して、少しでも現地語でのコミュニケーション能力を高めましょう。ヒアリングを磨くためには、NHKのテレビやラジオでやっている外国語会話講座が役立ちます。
交換留学の場合は、選考試験合格後も英語力の向上を課せられます。英語のテストで基準点以上を取らないと、現地の学校が受け入れてくれないからです。合格できないと何度も再試験を受ける羽目になり、期限までに合格できないと派遣取り消しになります。
9.出発に向けて準備
パスポートやビザ、スーツケースなどを準備し、現地のお金を用意します。海外で病気になると医療費が高額なので、海外渡航保険も必要です。予防注射が必要となる国も少なくありません。交換留学の場合は、いくつも作成しなければならない英文書類(英語の健康診断書など)があり、出発前にホストファミリーへの自己紹介英文レターを出します。持っていった方がいいものについては、体験者のレポートなどを参考にしましょう。

![]()
